2022.07.23
アドラー心理学って名前しか知らない。
アドラー心理学とは:ニヒリズムの対極にある思想であり、哲学。「もうひとつの哲学」とも呼ばれる。オーストリア出身の精神科医アルフレッド・アドラーが20世紀初頭に創設した「個人心理学」のことを、日本では「アドラー心理学」と呼ぶ。
「所有の心理学」ではなく「使用の心理学」、人間理解の真理そして到達点とされる。
現実、すべての人に好かれるなんて、不可能なこと。
「嫌われている」状態を、ふつうとして受け入れる、という哲学?
・・・人は誰もが幸福になれる!!!
世界を直視する「勇気」があるかどうか、がカギらしい。
\【30日間無料】12万冊以上のオーディオブックが聴き放題 /
AMAZON Audibleを今すぐ体験する>>こちらをクリック
いつでも途中解約OK

世界を変えるのは自分
舞台は1000年の都とうたわれた古都。「人生はどこまでもシンプルであり、人は今日からでも幸せになれる」と説く哲学者のもとへ「世界は矛盾に満ちた混沌としか映らない、幸福などありえない」と主張する青年が訪ねていく。
青年は自分の悩みを哲人に打ち明けつつ、対話を重ねていく。
人のことは冷静に、客観的に見ることが出来る。青年の立場に立ちつつ、哲人のアドラー的解釈がすんなりと入ってくる。
人は、客観的な世界に住んでいるのではなく、自らが意味づけをほどこした主観的な世界に住んでいる。
あなたの「目的」は、「他者との関係のなかで傷つかないこと」(悩みを消し去るには、宇宙のなかにただひとりで生きるしかない)。
・原因論(トラウマ)の住人であり続けるかぎり、一歩も前に進めない。過去の「原因」ではなく、いまの「目的」を考える。経験によって決定されるのではなく、経験に与える意味によって、自らを決定できる。
・目的論:目的を達成する手段として、不安や恐怖といった感情をこしらえている。われわれはみな、なにかしらの「目的」に沿って生きている。
「不安だから、外に出られない」のではなく、「外に出たくないから、不安という感情をつくり出している」。
いまのあなたが不幸なのは、自らの手で「不幸であること」を選んだから。
人は、いろいろと不満はあったとしても「このままのわたし」でいることのほうが、楽で安心だから。
怒りとは出し入れ可能な「道具」である。
人は怒りを捏造する:大声を出す、という目的が先にある。大声を出すことによって、ミスを犯したウエイターを屈服させ、自分のいうことをきかせたい。その手段として、怒りという感情を捏造した。
これまでの人生になにがあったとしても、今後の人生をどう生きるかについてなんの影響もない。
あなたはあなたのライフスタイルを、自ら選んだ。自分で選んだものなら、再び自分で選びなおすことも可能。
ギリシア語の「善」(agathon):自分のためになる/「悪」(kakon):ためにならない
ソクラテスのパラドクス:誰ひとりとして悪を欲する人はいない。
性格や気質:ライフスタイル イコール 人生のあり方
劣等感とは「客観的な事実」ではなく「主観的な解釈」。
短所ばかりが目についてしまうのは「自分を好きにならないでおこう」と決心しているから。
155センチという身長に、わたしがどのような意味づけをほどこすか、どのような価値を与えるか?
孤独を感じるのにも、他者を必要とする。
優越性の追求:無力な状態で生まれる人間は、その無力な状態から脱したいと願う、普遍的な欲求を持っている。理想に到達できていない自分に対し、まるで劣っているかのような感覚を抱く。
劣等感(努力や成長を促す)ではなく、劣等コンプレックス(自らの劣等感をある種の言い訳に使い始めた状態)であるなら、自らのためにならない。
見かけの因果律:本来何の因果関係もないところに、あたかも重大な因果関係があるかのように自らを説明し、納得させてしまう。
優越コンプレックス:あたかも自分が優れているかのように振る舞い、偽りの優越感に浸る。もしも自慢をする人がいるとすれば、それは劣等感を感じているから。
不幸自慢:自らの不幸を武器に、相手を支配しようとする。その人は永遠に不幸を必要とする。
健全な劣等性:他者との比較のなかで生まれるのではなく、「理想の自分」との比較から生まれる。
「自分が正しい」と思うと、生きるのが苦しくなる。
人は、対人関係のなかで「わたしは正しい」と確信した瞬間、すでに権力争いに足を踏み入れている。誤りを認めること、謝罪すること、権力争いから降りること、いずれも「負け」ではない。
人は学校で、社会で、他人との競争を強いられることが多い、、、他者と比較するから生きるのが苦しい。
「人々はわたしの仲間だ」と実感できれば、世界の見え方は変わる。
自らの人生を、自らのライフスタイルを、自分の手で選ぶ。
行動面 ①自立すること ②社会と調和して暮らせること
行動を支える心理面の目標 ①わたしには能力がある、という意識 ②人々はわたしの仲間である、という意識
人は「この人と一緒にいると、とても自由に振る舞える」と思えたとき、愛を実感することができる。
「あの人」の期待を満たすために生きてはいけない。他者の期待など、満たす必要はない。他者もまた「あなたの期待を満たすために生きているのではない」。
対人関係の入口である「課題の分離」とはなにか?
あらゆる対人関係のトラブルは、他者の課題に土足で踏み込むことーあるいは自分の課題に土足で踏み込まれることーによって引き起こされる。
誰の課題かを見分ける方法はシンプル:「その選択によってもたらされる結末を最終的に引き受けるのは誰か?」
「馬を水辺に連れていくことはできるが、水を呑ませることは出来ない」:自分を変えることができるのは、自分しかいない
自由とは、他者から嫌われること:他者の評価を気にかけず、他者から嫌われることを怖れず、承認されないかもしれないというコストを支払う。
対人関係のカード(常に自分が握る)という観点:殴られたから父との関係が悪い、ではなく父との関係をよくしたくないから殴られた記憶を持ち出している。
人間をこれ以上分割できない存在だととらえ、「全体としてのわたし」を考えることを「全体論」と呼ぶ。
自己への執着(self interest)を他者への関心(social interest)に切り替えていく。
・対人関係の出発点:課題を分離すること
・対人関係のゴール:共同体感覚(social interest:他者を仲間だと見なし、そこに「自分の居場所がある」と感じられること)をもつこと。
人からどう見られるかを気にかける生き方こそ、自分にしか関心を持たない自己中心的なライフスタイル。
人からどう見られるか、あまり気にしない(自分)のも、どうだろうと思うけど、自分が「生きるのがつらい」と思ったことはない理由がわかった。
共同体感覚とは?

幸福な対人関係において、欠かせないという「共同体感覚」って?
共同体へのコミットとは:「わたしはこの人になにを与えられるか?」
所属感とは:生まれながらに与えられるものではなく、自らの手で獲得していくもの。
関係が壊れることだけを怖れて生きるのは、他者のために生きる、不自由な生き方。
目の前の小さな共同体に固執せず、より大きい共同体の声を聞くべき。
すべての対人関係を「縦の関係」ではなく、「横の関係」とする。
「横の関係」=「ほめてはいけない」「叱ってもいけない」(ほめる、叱る:背後にある目的は操作)
人にほめられること:「自分には能力がない」という信念を形成していく。
いちばん大切なこと:他者を評価しない。
劣等感とは、縦の関係の中から生じてくる意識。対人関係を縦でとらえ、相手を自分より低く見ているからこそ、介入してしまう。
横の関係に基づく援助のことを「勇気づけ」(馬を水辺に連れていく:課題に立ち向かうのは本人、決心するのも本人)と呼ぶ。
人は感謝の言葉を聞いたとき、自らが他者に貢献できたことを知る。
「わたしは共同体にとって有益なのだ」と思えたときにこそ、自らの価値を実感できる。
人は、自分に価値があると思えたときにだけ、勇気が持てる。
他者から「よい」と評価されるのではなく、自らの主観によって「わたしは他者に貢献できている」と思えることが大事!
対等な関係を築く:ライフスタイルの大転換=意識の上で対等であること、そして主張すべきは堂々と主張することが大切。
自己肯定ではなく、自己受容。
1 自己への執着(self interest)を他者への関心(social interest)に切り替える。
2 「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」の3つが必要。
自己受容:「肯定的なあきらめ」できない自分をありのままに受け入れ、なるべく前に進んでいくこと。「変えられるもの」と「変えられないもの」を見極める。
他者信頼:他者を信じるにあたって、いっさいの条件をつけないこと。裏切るか裏切らないかを決めるのは、他者の課題。あなたはただ「わたしがどうするか」だけを考えればいい。信頼することを怖れていたら(「裏切られたとき」受ける傷の痛みにばかり注目)結局は誰とも深い関係を築くことができない。
仕事の本質は「他者貢献」:「わたし」を捨てて誰かに尽くすことではなく、むしろ「わたし」の価値を実感するためにこそ、なされるもの。
他者貢献(わたしは誰かの役に立っている。わたしは共同体にとって有益である)は目に見える貢献でなくともかまわない。主観的な「貢献感」を持てれば、それでいい。
対人関係の中で不愉快な思いにさらされることはある。
攻撃してくる「その人」に問題があるだけであって、決して「みんな」が悪いわけではない。
(ユダヤの教え:10人のうち1人はどんなことがあってもあなたを批判する。2人は互いにすべてを受け入れ合える親友になれる。残りの7人はどちらでもない人々だ。)
幸福の定義:幸福とは、貢献感である:承認欲求を通じて得られた貢献感には、自由がない。承認欲求にとらわれている人は、いまだ共同体感覚を持てておらず、自己受容や他者信頼、他者貢献ができていない。
共同体感覚さえあれば、承認欲求は消える。
他者からの承認は、いらない。
安直な優越性の追求とは:特別に良く/悪くあろうとすること。
他者の注目を集め「普通」の状態から脱し「特別な存在」になること。
普通であることの勇気:わざわざ自らの優越性を誇示する必要などない。怠惰な自分を受け入れる。
自分を無条件に受け入れることが出来れば、他人に対しても同様に出来るはず。
ダンス・ダンス・ダンス
人生=いまこの瞬間をくるくるとダンスするように生きる、連続する刹那。
ダンスを踊っている「いま、ここ」が充実していれば、それでいい。
ダンスを踊ること イコール 旅:過程そのものを、結果とみなす。
・「いま、ここ」を真剣に生きること、それ自体がダンス。
・人生の嘘:人生における最大の嘘、それは「いま、ここ」を生きないこと。過去を見て、未来を見て、人生全体にうすらぼんやりとした光を当てて、なにか見えたつもりになること。
・人生の意味とはなにか?人はなんのために生きるのか?:アドラーの答えは、「一般的な人生の意味はない」というもの。「人生の意味は、あなたが自分自身に与えるもの」
・困難にあったときにこそ前を見て「これからなにができるのか?」を考える。
人生を物語に見立てると、その物語に沿った人生を送ろうとしてしまう。
物語の先には「ぼんやりとしたこれから」が見えてしまう。
わたしの人生はこうだから、そのとおりに生きる以外にない、悪いのはわたしではなく、過去であり環境なのだと。
世界とは他の誰かが変えてくれるものではなく「わたし」が変えるもの。
「わたし」が変われば「世界」が変わる。
\【30日間無料】12万冊以上のオーディオブックが聴き放題 /
AMAZON Audibleを今すぐ体験する>>こちらをクリック
いつでも途中解約OK
このブログを読んでいただいてありがとうございます。
あなたに思いがけないハッピーがありますように!



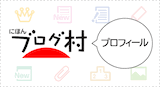


コメント