2022.08.10
お寿司は「好きじゃない」と思っていた。
「すご〜く好き」って、思ったことがなかった。
回転寿司は落ち着かないし、高級店に漂う緊張感も苦手だった。
今日は、真夏の暑い気温の中、半日外を出歩いた。
昼に少ししか食べず、夕方になり、空腹状態でお寿司を食べた。
人生で初めて「お寿司って美味しい!」と思った、、、。
江戸時代、労働者が屋台でつまんでいたというお寿司。
日常生活の工夫から生み出され、時代を超え進化した食文化。
お寿司は、世界的にも超有名な日本の美食文化。
今日は、ついに美味しさが分かった「おすし」について調べてみた。

おすしのはじまり
意外なことに、おすしの発祥地は日本ではなく、東南アジアだった。
当時、山岳地帯に住んでいた民族が、入手困難だった魚を長期保存するための方法として考えた「熟鮓(なれずし)」と呼ばれる発酵食品がおすしの起源と言われている。
最初のおすしは、魚を米飯と塩で発酵させて酸っぱくした発酵ずし。
酢は使わずご飯は食べない(発酵のために使う)ものだった。
日本においては、奈良時代に「熟鮓(なれずし)」は貢物として朝廷へ献上されていた。
鎌倉時代になると、日本でも残り物の魚を利用した熟鮓が登場するようになる。
おすしの始まりは、発酵した魚を食べるために生まれたものだった。
ご飯も食べるおすしのはじまりは?
室町時代には、発酵期間を短くして、ご飯も食べる「なまなれ」(発酵を浅くやめるから魚も生々しいため、こう呼んだ)が誕生した。
おすしには食べどきというものができ、食べる日から逆算して、おすしを作ることも可能になった。
江戸時代には、おすしはさらに庶民へと浸透した。
江戸半ばには、ご飯を発酵させつつ、酢も混ぜるようになった。
18世紀には、一般庶民の間で「早ずし」(飯にお酢と塩で味付けしたもの)が食べられるようになった。
天皇家、将軍家、大名家などでは、あい変わらず「なまなれ」を食べていた。
彼らにとって、伝統とは守るものであり(おすしも例外ではなかった!)幕末になっても、江戸初期以前の「なまなれ」を作ったり売ったりする店が、まだ残っていた。
今のお寿司に近い「早ずし」は庶民だけのごちそうだったらしい。

現在のお寿司のはじまり
すし飯で作る現在のお寿司は、いつ頃生まれたのか?
江戸時代中期1700年代前半頃に生まれた「早ずし」が現在のお寿司の原型。
「早ずし」は、飯にお酢と塩で味付けしたもの。
待たずに、すぐに屋台で寿司を食べられるようになった。
江戸の街では、単身の男性が多く、「すし」「蕎麦」「天ぷら」などの屋台が繁盛していた。
「握りずし」が誕生する以前は、「箱ずし」が人気だった。
江戸時代中期には「巻きずし」「棒ずし」など、様々なお寿司が作られるようになった。
「握り寿司」はいつ頃生まれたのか?
江戸時代後期1800年代前半頃、100万の人々が暮らす大都会となった江戸の街で、「握り寿司」が考案された。(考案者は不明)
初めは、おむすび並みの大きさで、切り分けて食べられていた。
現代の「1皿に2貫盛る」スタイルは、当時の名残でもあるという。
当時の「握り寿司」は、江戸前で獲れた魚貝を下処理したタネと、お酢と塩で味付けしたすし飯が握られた。
華やかな江戸の街で生まれた「握り寿司」は、当時も人気の食べ物だったのだろう。
「巻き寿司」の誕生
江戸時代の半ば、宝暦から天明年間の頃、江戸の町の料理屋で酒を飲んでいる商店の主人がいた。
商店とはいっても大坂の大店ではなく、江戸の札差(米の売買の仲介人)の当主。
そして酔いが回ってきたのか、料理人に文句をつけた。
「オレはここにある料理なんか、食い飽きた。今までに食ったこともないようなもの、たとえばこのサバずしをメシと魚とがひっくり返ったような寿司にしてみろい」やらと。
料理人は一生懸命に考えて、寿司のご飯とサバの位置を逆転させた。
魚にご飯を合わせるのではなく、魚を細い芯にして、その周りをご飯で固め、輪切りにして出そうとしたが、外側にご飯が出ると、手にべたつく。
そこでご飯の外側に、和紙や魚の皮を巻きつけた。
すると今度は、いちいち口の中から和紙や魚の皮などを出さなければならない。
そこで、そのまま食べられるもので巻いてみた。
そうして「巻きずし」が生まれて、やがて全国に広がる。
海に近いところではノリやコンブ、ワカメなどが、山の中ではタカナの漬け物などが巻く材料として使われた。
芯は、魚から卵焼きやかんぴょう、ニンジンなどへと、精進モノに変わっていく。
携帯に便利で、とても食べやすい「巻き寿司」は、お弁当に大活躍な美味しいお寿司!
「稲荷ずし」の誕生
油揚げの中に、すしご飯。
この稲荷ずしは、出始めた江戸末期には、切られて売っていた。
切って売るので、油揚げは四角いのが決まりだった。しかし今日では、東日本は四角なのに対し、西日本は三角。
境界線は石川県から岐阜県、そして三重県へと抜けている。このラインは「関東」と「関西」を分ける線(愛発、不破、鈴鹿の関を結ぶ線)とも一致し、正月雑煮の四角と丸の境界。
油揚げの形だけではなく、中に詰めるすしご飯も、何も混ぜないか、混ぜても麻の実やゴマていどの白いすしご飯である東方に対し、さまざまな具を混ぜた五目ずしを詰める西方と、東西が別れる。
稲荷ずしはふつうのすし屋では、あまり好まれるものではなかった。
一つは油で、手がベタつくから。
もう一つの理由は、稲荷ずしは安いため、自分たちの握るすしとは違うのだと、暗に主張していた為。
稲荷ずしは、お手頃で満腹になれて、甘辛い味がおやつ感覚なのが良い!
「ちらしずし」の誕生
江戸時代後期の料理本『名飯部類』(享和2年 1802)に「おこしずし」「すくひずし」というすしが出ている。
すしご飯に具を切り入れて混ぜ合わせ、箱に詰めて重石をかけておくというもの。
食べるときには、ご飯をヘラで掘り起こす。
現代、静岡県伊豆地方や京都府北部、佐賀県白石地方などに、わずかに残っている。
これらのすしは、宴席にこのまま出される。掘り起こすのは宴席にいるお酒の入った男の人。酔った手で四苦八苦しながら、小皿にとったすしは、せっかく押さえてあったのに見るも無残な姿。
「それだったら、最初から押さなくてもいいんじゃない?」ということで押さないすし「ちらしずし」ができた。
具材は「シンプルでもよし、豪華ならなおよし」な自由なもの。
現代でも、最も簡単にできるおすしとして知られる。
「ちらしずし」の類語に「五目ずし」というのがある。「どちらも同じ」とするのが今の日本。
しかし静岡県だけは、「白いすしご飯の上から具をふりかけるのがちらしずし」「具を混ぜてしまうのが五目ずし」となっている。
ちらしずしは、素人でも作りやすいのに、見た目に豪華で、ごちそう感満載!

一般的な寿司の定義
一般的にはシャリ(酢飯)とネタ(主に魚介類)を組み合わせた和食のことを、寿司と呼ぶ。
新鮮な魚介類以外にも、肉や野菜、卵などの食材がネタとなる場合もある。
海外におけるカリフォルニアロールなど、地域や店舗により、使用される食材や表記は異なる。
寿司の代表的な種類
握り寿司/巻き寿司/押し寿司/ちらし寿司/棒寿司/いなり寿司/手巻き寿司/軍艦
寿司における代表的な3つの表記
「すし」は「寿司」以外にも、「鮓」や「鮨」と表記される場合がある。
1寿司:現在、最もメジャーな表記。江戸時代に縁起担ぎで作られた当て字が由来となっており、ネタや種類に関係なく使うことができるため、一般的に広く用いられている。
2 鮓:3種類のなかでも、最古の表記である「鮓」。元来は発酵させて作るすしという意味であり、「酸し(=酸っぱい)」という、すしの語源を継承したもの。
3 鮨:「鮓」の次に古い表記。江戸前系のすしで用いられることが多く、それ自体を指す意味も、あわせ持っている。
ネタに刺し身が使われ始めたのは明治時代以降
製氷産業が盛んになった明治30年以降、漁法や流通の発展と相まって、これまで生の刺し身が扱えなかった寿司屋も、ネタを氷で冷やして保存できるようになった。
現代では一般的な、煮切り醤油をネタに塗って出す提供方法は、この時代に確立されたスタイル。
時は進み、大正時代初期。寿司店に電気冷蔵庫が登場するようになり、続々とネタの種類が増えて、サイズも小ぶりになった。
その後、関東大震災の影響で寿司職人が全国に散らばったことにより、地方にも江戸前寿司が広まったとされている。
順調な発展を遂げてきたおすしだけど、昭和時代、状況は一転する。
高度経済成長期、衛生上の理由から、これまでメジャーだった屋台の寿司店が廃止になってしまう。
しかし昭和33年、史上初の回転寿司が大阪で開業した。
そしておすしは、庶民的な食べ物としての地位を取り戻した。
手頃に食べることができる現代のお寿司は、このような歴史の流れを受けて存在している!
お寿司の豆知識&マナー
寿司職人さんとの距離が近い寿司屋さんへいったら、ぜひ話しかけてみよう。
その日のおすすめを聞いてみたり、好みを伝えたりすることで、充実した食事を楽しむことができる。

今日は、お寿司のマナーに初めて意識を向けて、お寿司を食べた。
日本文化としての寿司を食べるときの礼儀とマナー
✔︎ 握り寿司は箸ではなく手で食べる。
手づかみの食事が歓迎されない文化の日本では、箸で寿司を食べる光景が一般的。
食べ方は個人の好みだけど、ぜひ直接手に取って味わってみるのがいい。
寿司職人さんが技術を惜しみなく投じて握るお寿司は、口に入れた瞬間にちょうどよく溶けるように、空気の量まで繊細に調整されているもの。
そのため、箸に力を入れてしまうと、形が崩れて、こだわりの味を楽しむ機会を逃してしまう。
✔︎ 醤油はシャリではなくネタにつける。
目の前で寿司職人さんが握ってくれるタイプの寿司店では、ネタにタレが塗られた状態で提供される場合もある。
これは、シャリに醤油をつけることで起こってしまう、必要以上に濃い味付けや形の崩れを防ぐための配慮。
このような理由から、寿司店ではネタのみに醤油をつけることがマナーだと言われている。
マナーを知って、食べたお寿司はとても美味しかった!
深い歴史や、さまざま礼儀作法がある「お寿司」はとても奥が深いものだった。
歴史、豆知識&マナーの実践で、お寿司をもっと楽しもう♪
このブログを読んでいただいてありがとうございます。
あなたに思いがけないハッピーがありますように!


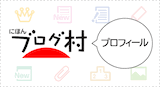


コメント